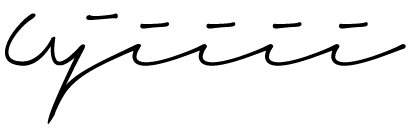Booklogs 2019 Jul-Aug
全然関係ないけれど、先日撮影したフレディーズのライブの一コマ
最近は結構本を読んでいる気がするので備忘録のため、軽くメモを残しておく。
『アメリカの夜』
フランソワ・トリュフォーの映画「アメリカの夜」の登場人物の設定や裏話、そして映画のスクリプトが記載された本。それぞれの配役の設定や、そもそもトリュフォーがなぜこの映画を撮ろうと思ったのかということが書かれており目からウロコ。1文目から「A movie about film making / なぜ映画についての映画なのか?」というところから始まるところからして最高でしかない。元々『シャイヨの伯爵夫人』という映画のオープンセットが残っていて、それを撮影に使おうという発想に至ったということが書いてあった。ストーリーはすべてトリュフォーが知りうる映画製作中の事実に基づくらしいということで、何重ものメタ構造が織り込まれた美しい「映画=人生」の構図が間違いなく成立しているんだなぁということを改めて感じる。また映画を見直してみようと想う。
『ペーパータウン』
映画版のウォールフラワーを見ているかのような気分になった。イケてないティーンが幼馴染の可愛い奔放な女の子の残した謎を巡って冒険をするという筋書き。サラサラと2時間くらいで読めてしまった。幡ヶ谷ブックオフ、ありがとう。高速道路をはしりながらビール瓶におしっこをするシーンはなんとなく共感を覚えた。忍び込んだ幼馴染の部屋でレコード棚を見て「デビッド・ギルモア、グリーンデイ、ガイデッド・バイ・ヴォイシズ、ジョージ・ハリスン、、、」という並びを見つけるシーンが有るのだけれど、そんな女の子が実際にいたら絶対引け目を感じて話しかけることもできないだろうな、自分は。と思う。
『ルーム・オブ・ワンダー』
交通事故で息子が植物状態(厳密に言えば違う)になってしまった母親の物語。息子が残した「やるべきことリスト」を発見し、その内容に沿って旅をするという話。海外の子供達はやることリストを作るのが好きだなと思いつつ(昔見た『ナイーブスーパー』もそうだったから)、それってとっても大事だよな〜と。東京に来て、ゴールデン街の居酒屋に行くシーンや、ロスト・イン・トランスレーションに出たカラオケに行くシーン、などがあった気がする。まぁまぁ面白かった。
『夏と恋』
ウィリアム・トレヴァーを初めて読んだが、イーユン・リーが影響を受けたということがわかる非常に精緻で質の高い恋愛小説だった。昔のアイルランドの風景や気候、人々の暮らし時代も国も知らない自分が容易にそれら想像できるくらい、巧みに文章を使いこなしている?ように感じられた。話自体は非常にシンプルだけれど、そこから得られる奥深さは作者の技量、センス、物事を捉える解像度の為せる技だろうなぁと感じた。久々にこういう純粋な読み物を読んだ気がした。
『灯台守の話』
ジャネット・ウィンターソンの最新作、ということだがこの作者のことは何も知らない。ただ一つ言えるのはこの小説がかなり最高だったということだけ。人生における大切なことを詰めたパンチラインだらけのラップを聴いているようなものなのだけれど、軽快で、ユーモラスで、本質的であり、美しい。
「日々の雑音のスイッチを切れば、まず安らかな静寂がやってくる。そして次に、とても静かに、光のように静かに、意味が戻ってくる。言葉とは、語ることのできる静寂の一部分なのだ」
話自体は、灯台に暮らす盲目の男、その灯台守と暮らす親をなくした少女、そしてその街の教会に仕える牧師の人生の話だ。灯台守は目が見えないから、大切なことを物語にして人々に話して聞かせる。そして主人公の少女にいう。自分自身が物語だと。語りえない話はないと。もし自分が最近読んだ本の中でおすすめは?と聞かれたら必ずこの本を挙げると思う。ちなみに、今の所のおすすめ本は
1. 『シカゴ育ち』スチュアート・タイベック
2. 『ヘミングウェイ短編集』アーネスト・ヘミングウェイ
3. 『千年の祈り』イーユン・リー
な気がする(たぶん明日には変わっていると思う)。ちなみに、シカゴ育ちは前付き合っていた彼女に貸したまま別れてしまったので、また買い直そうと思う。
『波止場日記』
波止場の鉄人と呼ばれたエリック・ホッファーの日記。エリック・ホッファーはまともな学歴もない野生の哲学者のような人で、スキッド・ロウに流れ着き、サンフランシスコの荷揚げを年老いるまで続けたという異色の経歴を持っている。最終的にはバークレーの客員教授にまでなり、全米の哲学系の討論番組にも出たほどらしい。自身が過ごした荷揚げに従事する人々の価値を考察していくのだが、それが日記の形式を通して断片的に綴られている。時折登場する複雑な関係の女性とその子供を思う気持ちがなんとも言えず優しい。その日々の合間に見せる鋭い洞察が彼自身の生活や視点から導き出されているということがとても貴重だと思う。言葉を扱う上では、どれだけ形而上学的に、メタ的に思想を語ろうとも主体である自身の経験や思想の軸から逃げることはできない。言葉と人生は不可分な関係にあると思う。だからこそ彼のような立場から物事を論じてくれるということに価値があると思う。優れた環境/生まれから生み出された哲学もまた重要であると思うが、こうした徹底的に地に根ざした思想というのは人の心を捉えてやまないと思う。
『はじめての構造主義』
エリック・ホッファーを読んで、彼のしていることはレヴィ=ストロースに非常に似ているな、と思った。そして先日読んだ岸さんの本にも通じるところがあると思い勉強をしてみようと思い手にとった一冊。※要するにフィールドワークを通して論拠を構築していくという部分期待していた内容とは違ったが、非常にわかりやすく構造主義の触りの部分が解説されており今後の学習の手がかりになった。レヴィ=ストロースの構造主義は当時全盛だった西洋哲学を根本的に破壊しうる可能性があったらしく、出た当初はかなり批判にさらされたらしい。それは何故かと言うと、歴史的に積み上げられた西洋哲学体系(=歴史を持たない民族の思想体系よりも優れているという前提)と、レヴィ=ストロースが行ったブラジルの民族の体系が「根本は同じじゃん!当価値じゃん!」ということが明るみにさらされてしまったからだ。それはエリック・ホッファーが知識人を批判する姿勢と似ている気がする。合わせて買った『悲しき熱帯』を読むのが楽しみになった。