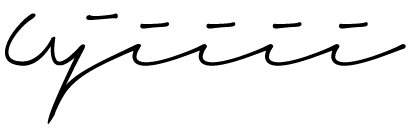A Romantic Composition
とても疲れている。体力的な辛さは問題ではなく、労働時間の長さも根本的な問題ではない。人の心が蝕まれる瞬間というのは精神的な重圧によるものが大きいのだなと初めてわかった。精神的なストレスと肉体的なストレスというのは不可分のように思えるが、本来は切り分けて考えられる。肉体的なストレスが仮に0だったとしても、精神的なストレスで人は容易く壊れてしまう。僕の周りで過去、そうした病に倒れていった人たちのことを見ていたけれど、それが今実体を伴ってどういうことなのか、どういう感覚で起きることなのかが理解できた。不意に涙が止まらなくなる、ベッドから起き上がれなくなる、そんなことは僕にはまだ起きていないけれど、おそらくその感覚はわかる。そしてこういったことはコントロールが全くできない。更に状況を悪化させる要因として、そもそも人はストレスを感じることには敏感だが、ストレスを与えることに関してとても鈍感であるということがあるのかもしれない。普段の振る舞いそれ自体が他人のストレスになっていることなんてよくあることで、常にそうしたことは忘れられがちだ。それが意図したものなのか、意図したものでないのかは究極的には関係がなく、ただ誰かを苦しめるている可能性があることだけは忘れてはならないのだろう。
理想を追い求めるということは、とても素晴らしいことだと思う。その一方で理想を追うことを強いることや、理想的な状態であることを強いるというのは、この手のストレスを生み出す大きな要因になっているように思える。それは理想的な状態というのは突き詰めると主観的なものだからだと思う。理想というのはある種絶対的で一元的なもののように思えるけれど、その実は複雑な形状をした多面体であり、特定の関係性の中でしか存在し得ない。何かを理想的だと思ったとき、それはその対象と自分との間にある関係値がとても高いということを示している。しかしそれが他者からみたときに理想的であるという保証はどこにもない。それと同時に、理想を追い求めると言う行為自体が正しいものであるという強迫観念のようなものがこの世の中には蔓延っている。「その理想」が自分にとって正しいものかどうかということや、理想を追い求めるという行為が正しいことであるということも、いくらでも疑う余地がある。だからとにかく押し付けがましい人とか、絶対的に正しいと思わせる価値観をさも正しいかのように振り回す人とは距離を置かざるを得ない。そんなものはない。
そんなことを考えながら、休みの日に会社に向かう途中に青山のスパイラルにいってミヤギフトシさんの「ロマン派の音楽」を見た。仕事をしすぎているせいで、文化的なことから長らく離れていた。好きな映画を見ることも、音楽を探すことも、ゆっくりと本を読んだりすることも満足にできない日々が続いていた。疲労がたまりすぎて頭も体もフラフラだったけれど、その時見たミヤギフトシさんの映像作品は、彼が自分にとって特別な作家だということを思い出させてくれた。誰にも押し付けたりはしないけれど、ある意味僕にとっては理想的だとも言っても良い。昔大阪で見た「The Ocean View Resort」を当時付き合っていた恋人と見たけれど、そのとき彼女は「感傷的すぎる」ことや「拙い英語」が笑えること、「映像作品、美術作品としての未熟さ」ということを指摘していた。彼女は彼女の尺度で評価をする。だけれど、僕にとってはその彼女が貶めた点はミヤギフトシさんの作品の素晴らしさであり価値だった。それから暫く、作中で流れたベートーヴェンの「弦楽四重奏15番 第三楽章」ばかり聴いていた。
「ロマン派の音楽」は沖縄に住むピアニスト、その息子と思われる人間、バイオリン弾きのアメリカ人の三人の視点が一人称、三人称で語られる。モニターは2台、スピーカーは3台、そして英語と日本語、英語字幕と日本語字幕が場面に応じて切り替わる。少し野暮ったい平凡な映像に沖縄の風景がぼやけながら映る。アメリカ人のパートは日本語訛りの英語で語られる。いくつもの視点が交差しながら物語が進んでいく。左右のスピーカーから分散して聞こえる会話や、モニタに映る映像の視点の違い、一人称と三人称の語り口が切り替わりながらストーリーが進行する。そうすると最初は朧気だったストーリーが像を結び、一つの体験として実体を伴った絵として立ちあがっていくように感じられるのが不思議だった。登場人物が実際の取材に基づいているのか、架空のペルソナなのかどうかはわからない。だからこれがフィクションであるかどうかもわからない。ただ至極パーソナルな物語を語っているだけなはずなのに、どうしてこうも胸にこみ上げるものがあり、そしてリアリティがあるのだろう?ここにミヤギフトシさん彼自身の一人称は含まれていない。彼固有の体験は語られていなくて、彼自身はこの物語の登場人物ではない。彼自身はどこにもいないのに、紛れもなく彼でしかないという感覚があった。この少しだけロマンティックな、どこにでもありそうな物語はミヤギフトシさんそれそのものだった。20分ほどの間、そのモニタの前に立ってスクリーンを眺めていた。僕以外には誰も見ている人はいなくて、十数秒画面を眺めて立ち去っていく人がほとんどだった。
自分自身を他者の視点によって語らせることは、ときに自分自身を自分自身で語ることよりも嘘がなく、公平で、純粋であるように思える。人は基本的に自分自身の存在を疑うことはしない。けれど、自分の周縁の存在を描ききることで、自分自身で存在を明示しなくても自身を表現することもまた可能だ。その関係は、彫刻と鋳造の違いに似ていると言えるのかもしれない。概念的に、一つの素材から実体を削り出すという彫刻的な営みというのは主観的で、空の空間をもたせることによって実体を浮かび上がらせる鋳造というのは客観的な営みのような気がする。そして主観的なほうがストイックでつらそうで、客観的なほうがサーカスティックで気楽である、ような気がする。自分に置き換えて考えるとすると、僕自身が自分のことを語ることは苦手だ、けれど好きなものについて延々と話を続けることはできる。好きなものについて話しているうちに自分のことを理解してくれたら嬉しいと思うし、それが理解されなかったら自分のことが理解されなかったかのように悲しいと思ってしまうこともあるかもしれない。だから自分自身の存在価値を誇示するような人は苦手だと思ってしまうきらいがある。もちろんどちらが良いとか悪いとかそういうはなしではないのだけれど、客観性=他人の視点で語るということがロマンチックな組成(A romantic composition=ロマン派の音楽)であるということ、そしてその組成が美しい多相性を持っているということを作品によって表現しきっているという点において、ミヤギフトシさんのしていることは僕にとっては疑いようのないくらい正しいことのように思えた。
亡くなった祖父の部屋の戸棚に、ベートーヴェンの「弦楽四重奏15番 第三楽章」が入ったクラシックのコンピレーションCDを見つけたのは何年も前だった。僕のパソコンにこの曲が入っているのはそのせいだ。祖母が亡くなる前、祖母と祖父は離れで二人で椅子に座りながら、大きな古い日本製のCDラジカセでよくCDを聴いていた。日によっていろいろな作曲家の曲が流れたけれど、「弦楽四重奏15番 第三楽章」は僕にとっては祖父や祖母を思い出す曲だ。「The Ocean View Resort」が、この曲に美しく彩りを与えてくれたことで、昔を思いながら安らぐことができるようになった。「ロマン派の音楽」もとても素晴らしいのだけれど、以前見た「The Ocean View Resort」の、「弦楽四重奏15番 第三楽章」の繊細な美しさがやっぱりミヤギフトシさんの作品の中では一番心に残っている。
今日は久々に仕事を諦めて早く帰り、友達と深夜過ぎまでコーヒーを飲んでいた。とても楽しかったけれど、以前よりも自分が口数が少なくなったり、人の話を聴いていない時間が増えているような気がする。そうしたことで、僕の周りの大切な人たちに迷惑をかけていないかどうかが少しだけ気になる。