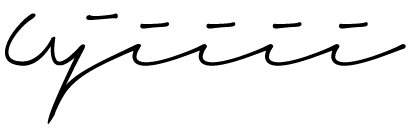SEE EVERYTHING ONCE / TRIP TO SOUTHERN DAY30
昨日夜に見たメイコンの雰囲気が良かったので、朝起きてからまたメイコンに来た。郊外の方の廃れた雰囲気を写真に撮るためだった。写真に残しておきたいと思える光景に出会えること、時間があること、元気であること(これは大事)、それらが重なったときは出歩いていても楽しさがある。郊外の退廃的な雰囲気や褪せた色のコントラストは見ていて嬉しさがある。かつて使われていたであろう建築物や車がそのまま放置され、時間とともに錆たり壊れたりしている。誰も直そうとしたり壊したりしようともせずただその場所に残されている。そうしたものがいつまでも残っていて欲しいというのは自分勝手なエゴだけれど、この手の美しさには飽きることはないだろう。
メイコンから車を走らせてマイルドヴィルという街へと向かう。ここはフラナリー・オコナーが暮らし、その生涯を終えた場所だ。マイルドヴィルの街は美しく整備されたスモールタウンで、彼女の家はそこから郊外へ向けて10分ほど車を走らせたところにあるらしい。この街の至る所に彼女ゆかりの場所が残されていたけれど、この日はサンクスギビングでその全てがやっていなかった。今日が国民的な祝祭日であることを完全に失念していたし、それはフラナリー・オコナーの暮らしていた家においても例外ではなかった。彼女が飼っていた孔雀と暮らしていたという家へアプローチするための緑道は封鎖されていた。無情にも閉じられたそのゲートを見つめ、もしかしたら誰も見ていないだろうし飛び越えて行ってしまおうか、、、と10分ほど逡巡したけれどどこかにカメラがついているとも限らないと思ってやむなくその道を引き返す。サンクスギビングに施設をわざわざ開けて待っていてくれるような善人はなかなかいない。彼女の家を訪れることは旅の中の大切な要素の一つであることは間違いがなかった。25歳で病気に冒され、39歳でその生涯を終えた彼女の人生は儚かった。「俺の人生を破壊したものは何かと聞かれたら、オコナーの小説だ」と僕のアメリカ人の友人は言っていた。彼女はその短い生涯においてその深い洞察力において南部の生活を描写することで人間本来の性質を描き出した、とはよく言われる。ナラティブな視点で語られる静かな狂気や暴力性は物語を通して読む人の人生すらある意味で破壊してしまうほど濃密なものだ。文面から見れば敬虔なキリスト教徒とは思えないほどに神という存在を「信じていない」ように見える。彼女の使うユーモア(と言って良いのかわからないが)は澄み切った暗黒というか、どこまでいっても救いがない、純粋な救いようの無さだ。一片の希望すらない。しかし彼女にとって小説を書くことだけが現実に相対する方法であり唯一の希望であった。救いようのなさ、そしてユーモアという点で言えば僕の愛する作家のカート・ヴォネガット・ジュニアと相通ずるところがあるが、その視点はより冷徹で現実的で、必然的なように感じられる。彼のように空想を描くこともなく、身辺に起きうることを深く深く描写し、ニヒリスティックなユーモアを混ぜることもない。彼女の描くユーモアは絶望と希望の妥協点にあるのではなくて、止揚点として使われている。信仰を善だとする価値観、善いことを信仰する宗教というものの現実と限界を緻密に描写することで、普遍的な善さというものが破壊的な暴力性を持ちうるということを表現している。だからこそ、見る人にとって彼女の描写する暴力が普遍性を獲得しているように感じられ、今でも人の心に深く突き刺さり、そして価値観をぐらぐらと揺さぶってくるのだと思う。そして僕は彼女の家のアプローチの前で苦し紛れにこのような考察をし、自分の救いようのない計画性の無さに少しでも抗おうとしていた。彼女の暮らした家も牧場も何一つ見れなかった悲しみはこんなやっつけ仕事で癒えるようなものでは到底なかった。彼女が暮らしていた家、そして牧場のそばには今ではウォルマートやガススタンド、ディーラーショップが立ち並んでいて騒々しく車が往来していた。彼女の家のそばには小さな美しい教会があり、その脇には「オコナードライブ」と言う名前の小さな通りがある。その通りは深い美しい木立に包まれた住宅街で、森の中に大きな邸宅が均等な感覚で数件並んで建てられていた。紅葉した木々の葉が地面につもり、木の枝の先に残った黄色や赤い葉は大きな白い邸宅とコントラストを作り出していた。彼女の家の近くの教会に車を停めてその静かな教会の庭先で少しの間ゆっくりとしていた。秋の陽の光が小さな墓石を照らし出しているのは綺麗だった。
更にそこから北を目指して車を走らせる。エイセン、ボウマンという小さな綺麗な街を通り過ぎる。サウスカロライナ州とジョージア州の境にあるスミスレイクと言う名前の静かな湖の上を古びた吊橋が渡されている。その脇に車を停めて煙草を一本吸って休憩をする。夕焼けに染まる湖は黄金色の光を反射してとても眩しい。旅が進むにつれてどんどんと日が短くなっていくことを感じる。背伸びをして、大きく深呼吸をして、なんとか疲れをごまかして先へと進んでいく。サウスカロライナのグリーンヴィルという大きめの街についたときにはもう日が暮れていて、手早くドライブインでテイクアウトのハンバーガーを買って足早にその街を出た。夜のドライブは疲れているときにはすべきではないからだ。夜に田舎町を走っていると気がついたことが一つあった。それはサウスカロライナの田舎町では既にクリスマスのオーナメントが飾られていることだった。一つ一つの家の間隔が大きく離れているのだけれど、その家ごとに独自の飾り付けを施している。あたりは街灯もなくて真っ暗なのだけれど、家によっては屋根や窓のふちにそって電飾をあしらっているので家の大きさや形が遠くからでもわかった。大きく縦に長い出窓からは大きなクリスマスツリーが見えたり、軒先や広い庭にはトナカイやソリが既に準備されている家もあった。貧しい家でも壊れかけのフェンスに電飾をあしらってクリスマスを今か今かと心待ちにしているように見える。車のラジオからはDJが気を利かせてかけるクリスマスソングが次々と流れてくる。通り過ぎたボウマンの街では交通整備が必要なほど混んでいる店が1軒だけあって、それはクリスマスグッズを売っている雑貨屋だった。普段は静かであろうそのスモールタウンのダウンタウンは年に一度のクリスマスを祝うために街の人が長蛇の列を成してオーナメントやデコレーションを買い求めていた。ポール・マッカトニーのクリスマスソングを聴きながら、こうした地域のクリスマスは本当に尊いものなんだなと感じる。近くの街から遠く離れて娯楽もないこの街にも年に一度必ず訪れるお祝いの日、それを一ヶ月も前から前のめりで祝っていることはすごく素敵なことだと思う。クリスマスの楽しさは誰にとってもかけがえの無いものであったと気がつくことができたし、この静かな賑やかさは今にも遠くから鈴の音が聞こえてくるようだった。その高揚はカポーティの『クリスマスの思い出』を思い起こさせる。
”十一月も終わりの朝を思い浮かべてほしい。二十年以上昔の、冬近い朝だ。田舎にある、広くて古い家の台所を想像してほしい。ひときわ目につくのが、黒い、立派なかまどだ。もちろんそこには大きな丸いテーブルもあるし、暖炉もあって、その前には揺り椅子がふたつ並んでいる。暖炉はちょうどこの日から、冬にふさわしいゴウゴウと鳴る音を立てはじめたところだ。”
そう、田舎のクリスマスは11月の終わりから始まっているのだ!
深夜にガソリンスタンドに立ち寄ってガスを入れると、自分の吐く息が白くなっていることに気がついた。ついこの間までTシャツで過ごしていたので忘れていたけれどもう12月になるところだ。気温を見てみると既に1桁に落ち込んでいることを考えると、もう自分がアパラチア山脈の麓にいるのかもしれないと思った。この旅で危惧していることがあるとするならばアパラチア山脈の道路が雪に閉ざされたり、走行中に大雪に見舞われることだ。アラスカからはなんとか生還ができたけれど、同じようなシチュエーションに遭遇したらまた生きて帰ってこれる保証はない。寝る前に天気予報と道路情報をひたすら確認し続けて、明日の安全を確保することに躍起になった。そんな深夜のトラックストップに、野暮ったい白いセーターを着た親子の三人組が農作業用のトラクターで乗り込んできたと思ったら、手に大きなチキンのバスケットと顔の大きさほどもあるジュースのカップを抱えて出ていった。彼らを見ていたらこの寒さも雪への不安もなんとかなりそうだと思ってしまって、調べるのをやめた。明日の朝は凍えるほど寒くなりそうな予感がしていたので、身体に入念に毛布とブランケットを巻きつけてパーカーのフードを被って眠りについた。