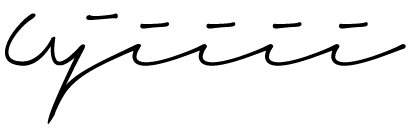SEE EVERYTHING ONCE / TRIP TO SOUTHERN DAY24
以前学校の先生とアメリカ文学に話をしたことがあった。たいそう頭が良かった彼のお気に入りはフラナリー・オコナーだった。アメリカ文学における一つの系譜として南部を舞台に描かれたものがあるけれど、フラナリー・オコナーはその代表の一人だった。『賢い血』しか読んだことがなかったし、それもだいぶ昔だったからその話をした時にはあまり会話が続かなかったのだけれど、フラナリー・オコナーという名前を生徒から聞いたのは彼の20年以上の教師としての生活の中で初めてだったらしく、そのあとYoutubeに違法アップロードされていたジョン・ヒューストンの『Wise Blood』のリンクを授業中に送ってきた。僕の中で南部物の中で印象に残っているものはいくつかあるのだけれど、一番良く覚えているのはウィリアム・フォークナーについてだった。適当に古本屋で買った短編が面白くて、その中でも一番良く覚えていたのは「エミリーに薔薇を」と題された短編の一節だった。当時バンドサークルに入っていた僕は、その曲の名前をゾンビーズの曲名から来ていることを先輩から教えられてこの作家について興味が湧いた。なぜイギリスのバンドがアメリカ南部の音楽を?と今では思うけれど、その時のぼくはアメリカについて何も知らず、フォークナーが南部を代表する作家であることも、「エミリーに薔薇を」の舞台が南部の街であることも取り立てて意識することなく面白い小説だと思って読んでいた。エミリーが殺した青年の遺体を後生大事に抱えながら家から一歩も出ずに、社会との関わりを断って生き続け、そして死ぬ。誰にも祝福されないその死に際と、見たことも想像したこともない情景の描かれ方がずっと頭のどこかに残っていた。『アブサロム、アブサロム!』『八月の光』『サンクチュアリ』と、分厚い彼の本をうんうんと頭を唸らせながら背伸びして読んでもさっぱりわからないこともあったけれど、読んでいくうちにそれが昔のアメリカの南部の雰囲気なのだろうということは僕にでもわかった。メンフィスからミシシッピ州のほうに少し戻ると、オックスフォードという名前の街がある。ここはそのフォークナーが生まれ、ずっと暮らしていた街だった。街というよりもスモールタウンくらいの規模のその街はこれまで僕が見てきたミシシッピ州の雰囲気とは全くかけ離れていた。これまで見てきたミシシッピ州の雰囲気といえば陰鬱とした空気と荒れ果てて閑散とした町並みだったけれど、このオックスフォードは街路樹も綺麗に整備され、家並みは立派で、ダウンタウンはおしゃれなお店が立ち並び人々で活気に溢れていた。白人しか歩いていなかったし、どんな小さな家からも荒廃した雰囲気は漂ってこなかった。同じ州の中でこれほどの違いがあるなんて、と驚きを隠せない。まるで別の国のように、あのブルースハイウェイとここが地続きであることが信じられなかった。そのダウンタウンから車でほんの5分くらい走ったところにある森の奥に、フォークナーが死ぬまで住んでいたローワンオークという場所がある。周りの家から少し離れていて、彼の家にたどり着くのに林道を2分くらい歩いた。森のなかの開けた場所にシンプルだけれど大きな家が立っていた。玄関に通じる道の両脇には高くそびえるオークの木が何本も植えられている。今では僕のように観光目当てで訪れる人も多いのだろう、家の中は観光施設としてしっかりと整備がされていて、受付にはやる気のなさそうな近所の大学生の女の子が座って対応をしていた。
彼の家は華美な装飾などはされておらずいい意味で生活感の残った空間だった。気品の感じられる家具の数々、壁紙や照明の意匠。それらは彼が決して貧しい暮らしをしていたわけではないことを物語っている。彼の書斎や寝室の壁には彼が残した小説のプロットが鉛筆で書き込まれていて未だ消えることなく残っている。ベッドの周囲に書き込まれた筆跡は彼自身の小説にかける情熱というよりも、彼自身のユーモアが表現されているように見えた。彼の著作はヨクナパトーファ郡という彼が考えた架空の街を舞台に広げられる、そしてそれは「エミリーに薔薇を」も同様。孤独で悲惨な人生を送ったエミリーが暮らしていた片田舎の家はもしかしたらこの彼の家なのかもしれないとふと思った。フォークナーは生きている中でのほとんどの時間をミシシッピ州で過ごし、その人生のなかの30年をこのローワンオークで過ごしていた。他人との関わりを断ち、同じ場所に住み続けるという彼の生活がこの家の暮らし、そしてエミリーの暮らしにに現れているような気がしたからだった。少なくとも、彼は小説の題材となるものを求めてどこかに旅に出たりするような人間ではなかった。それでいてなお、彼は人生を書くことに費やすのに十分な体験を得ていた。というよりもこの街で繰り広げられる出来事を距離を置いて冷静に捉えていたのだろうと思う。この街に当時住んでいた人々の暮らしも、おそらく似たようなものではなかっただろうか。このローワンオークの窓からは美しい庭と小さな牧舎と森しか見えない。しかしその向こう側にもきっと似たような暮らし、表面上は美しいがどこかに深い歪みが隠された暮らしがあることに気がついていた。彼が架空の街としてこの土地を描いたのはこの街の存在をぼかすためではなくこの街であることの暗示であり、彼の描く架空の街に暮らす人々の暮らしはこの地域に住む人々の暮らしだった。彼の人生は小さな円の中で収まるものだったかもしれないけれど、それを架空の街とすることによってその円の半径は広がり続け、やがてはアメリカ南部の生活を映し出す鏡になった。この小さな街の暮らしは南部の抱える闇の相似であるということは、彼がピューリッツァー賞を受賞したことによって証明されたはずだ。彼は直接的に南部の抱える闇に立ち向かうことができなかったから、ひっそりとした森の中に建てられた家の中の一室から、ひたすらに彼の見えるものを書き続けたのだろうと思う。
彼の家をあとにしたあとに、もう一度オックスフォードの街に戻ると本屋を見つけたので入ってみた。ミシシッピブックスと言う名前の素敵な本屋で、控えめに見積もっても僕がこれまで見てきた本屋の中では最高の場所といってもいいと思う。2階建てのこの本屋の二階にはテラスがありオックスフォードのダウンタウンを一望できる、そしてそのテラスにはベンチが置いてあり、カフェで買ったコーヒーもその場で飲むことができた。もちろん気持ちのいい風も吹いているし、上から通りを走る色とりどりの車や、ロータリーをぐるぐると回る高級車を見ているのは気分がよかった。ミシシッピ州の作家のコーナーは充実していて、やはりフォークナーは一番に取り上げられている。その脇には地元の写真家が撮影したヨクナパトーファ郡をモデルにした写真集が置いてあった。壁には著名な作家や政治家のポートレートが所狭しと敷き詰められ、観光客と思しき人達がその写真を写真に撮って喜んでいる。良い本屋のある街はいい街だ、と言う言葉に従うのならばこの街はきっと世界で一番いい街であることになるのだけれど、きっとこの街の歴史はそんなに単純ではなかっただろう。この本屋のテラスでこの街が夕暮れに染まっていくのを見届けたあと、この素晴らしい本屋のことを忘れないためにトートバッグを買った。次の目的地のアラバマ州に向かって車を走らせた。田舎道を走っている途中、もしかしてこの道は『八月の光』の冒頭で主人公のリーナがアラバマから歩いてきたその道なのではないかと勝手に思っていた。荒涼とした大地と遠くに見える森、そして日が沈みかけた深い青い空はその光景にぴったりだと思った。BGMはお決まりのようにアラバマ・シェイクスを聞いていたのだけれど、彼らの力強い歌声を聞いていると自然に涙が出てきた。車の中で音楽を聞いているとたまにやたらと心に沁みる瞬間があって、それはいつ来るかはわからない。フォークナーの小説のことをぐるぐると考えていたせいかもしれないし、オックスフォードの街と僕が訪れたミシシッピ州のその他の街の雰囲気の違いのせいかもしれない。彼らの歌の力強さが歴史的に背負った悲しみと深い部分で根がつながっているように思えたし、実際にそうではなかったとしても、僕の中でその悲しみと歌が結びついてしまっていた。そんな瞬間にみる夕暮れは本当に美しかった。