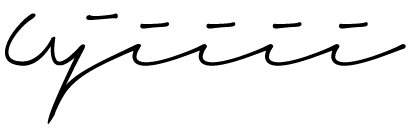SEE EVERYTHING ONCE / TRIP TO SOUTHERN DAY23
朝起きてメンフィスへ。一日でミシシッピ州を南から北へと渡ってきただけあって身体がだいぶ重く疲れが溜まってきている。メンフィスの南側のサウスヘイブンというエリアから順に車で回っていく。街から離れたエリアはかなり荒廃した雰囲気が目立つ。調べてわかったことだけれどメンフィスは全米屈指の危険地域で、特に人口から見た殺人率の高さは群を抜いている。そういう情報を頭に入れると、郊外を歩いている人たちや壊れた建物の並ぶエリアを通り過ぎるのにも緊張がつきまとってくる。サウスヘイブンの辺りにはアル・グリーンが牧師を務めている教会があるらしい。彼がまだ現役で歌っていることも、ましてや牧師を田舎町の片隅でやっているなんてまったく想像もできない。閑静な住宅街の中にその教会はあった。教会の前の通りには「Al Green」と書かれたサインが立っていた。その通りを100mくらい進んでいくと開けた土地があり、そこにこじんまりとした質素な作りの教会がたてられていた。あいにく、この日は日曜日ではなかったから教会で行われるミサにも出れなかったのだけれど次の機会には絶対に体験してみたい。そのミサではやはり彼の歌を聴けるらしいのだけれど、世界的にも有名な彼がこんな素朴な場所で牧師をしているなんて全然イメージもつかないけれど、その空間が間違いなく素晴らしいものになっているであろうことだけは想像に難くないと思う。
メンフィスといってまず思い出されるのはジャームッシュの『ミステリー・トレイン』だった。あの映画に出てきた永瀬正敏と工藤夕貴のかっこよさにはもちろん痺れたし、映画自体の持つチグハグな雰囲気は強く印象に残っている。当時、カール・パーキンスが誰だかわからなくて調べてみると、彼がメンフィスにある有名なサンスタジオで録音したということがわかって、それでメンフィスという街のことを覚えていたのだと思う。街を歩いているとすぐにそのサンスタジオは見つかるのだけれど、今では音楽が好きの人たちの観光地になっていた。ちょっとだけ悪趣味な大きなギターのオブジェを見た時に、こんなのあったっけなぁと思ったりしたのだけれど、それはまさに映画の中に現れたサンスタジオの見た目と一緒だった。通りを歩けばこの街で活動をしてきた有名なミュージシャン、例えばBBキングやオーティス・レディングだとかそういった人たちの記念碑が次々に現れる。映画の中だと銃声が響くゲットーのようなホテルが印象的でわりかしダークな印象を持っていたのだけれど、この日は雲一つない快晴で気持ちが良くいつまでも歩いて回れそうな気がしていた。メンフィスというとNBAのチームがあるくらいだから大都市なんだろうと勝手に思っていたけれど、歩いて回ることが苦にならないくらいにはこじんまりとした街だった。出歩いている人たちもそこまでいないし、街は静かだった。『ミステリー・トレイン』で使われたレストランがあるということでサンスタジオから少し歩いて通りを下っていってアーケードレストランという名前の洒落たダイナーに入る。外装も内装も店員も昔の雰囲気がしっかりと残されている。オーティスやビートルズがBGMで流れている。頼んだフレンチトーストはポーチドエッグが添えられていてとても美味しくボリュームが満点。歓談する常連客と店員のやりとりは見ていても楽しげで、この空間にずっと流れている雰囲気を感じさせる。「やあみなさん!」と言いながら店内に入ってくるおしゃれな黒人の家族、それに対して「今日もようこそ!」と答える店員の人たち。あたりを見ていると黒人も白人も、若者からお年寄りまで楽しげな雰囲気を醸しながら各々の時間を過ごしている。そのやり取りを眺めているだけでこの場所がかけがえのない場所だと感じる。観光地化されている場所ではあるものの、地元になじんだ歴史ある素晴らしいダイナーだった。壁には古めかしいサインやネオンが飾られる中、ひっそりとミステリー・トレインのポスターがかかっていた。店員の人がコーヒーのおかわりを注ぎにきたタイミングで「日本人はよく来るの?」と聞いてみたら「音楽や映画の好きそうな人がたまに来るわよ、こんな何もない街なのにねぇ」と言っていた。ただ、そのニュアンスにはどこか誇らしげな感じがしていたように思う。確実にこの街にしかない雰囲気が漂っているし、何よりこの場所で流れる音楽や築き上げてきた文化が他の街とは違うのだから。
そのレストランの近くにはキング牧師が暗殺されたロレイン・モーテルという場所がある。1968年の4月4日、このモーテルのバルコニーで友人たちと談笑していたキング牧師は一発の凶弾に倒れる事となった。彼が実際に亡くなった現場であるモーテル、そしてその犯人が狙撃に利用したモーテル向かいの建物は黒人の人権活動の博物館として再建されていた。平日だと言うのにモーテルの前には肌の色を問わずたくさんの人だかりができていて、キング牧師の死を悼む表情を浮かべていた。これまでモーテルに何度か泊まって部屋の前のテラスで煙草を吸ったりしながら友達と話したり、外の景色をゆっくり眺めたりしてきた。そうした時間を狙って襲ってきたのがその一発の銃弾だと思うと身の毛もよだつような思いがする。当時のアメリカの黒人に対する意識というのはそれほどまでに残酷なものだったことがわかるし、彼のように表立っていないところではより多くの、より凄惨な場面があっただろう。奴隷貿易が行われてから370年ほど経ち、ようやく状況が改善されつつある中でも、昨日ミシシッピ州でみてきたような光景は残っている。南側の街をドライブしていてたまにみる南部連合旗や、通り一本隔ててガラリと変わる街の雰囲気も、悲しくなるけれどそうした悲しい歴史の一部に思えてならないのだった。
道路脇にカラフルに彩られたミニクーパーが柱に刺さって空中に浮いているという奇妙なサインを見つけた。よくよくその看板を読んでみるとどうやらそこはドライブイン・シアターらしかった。生まれて初めてドライブイン・シアターというものに足を踏み入れる機会がここで来るとは、とにわかにテンションが上ってしまう。杉本博司やリチャード・ミズラックの写真の中でしか見たことがなくて、日本ではもう残ってすらいないドライブイン・シアター。それが2017年の現在でも使われていると思うと胸が熱くなる。カラフルに彩られた入場口から車を進めて当たりを見回す。その時初めてドライブイン・シアターの仕組みを知ったのだけれど、同時に上映できる映画はそのシアターが持つスクリーンの数だけあるらしい。写真でしか見たことがないから1つしかスクリーンが無いものと思っていたけれど、奥にある広い敷地内には多くて4つほどのスクリーンがあるようだった。それぞれの映画ごとに周波数が示されていて、その時間にその周波数帯に合わせれば車内のラジオから映画の音声が聞こえるようになっている。もちろん僕が行ったときは昼だったから映画は上映されていなかった。その辺に車を停めて歩いてその劇場内(と言っても外にあるのだけれど)に入っていく。初めて見たドライブイン・シアターは感動的だった。広々とした敷地内に白いスクリーンが4つそびえ立っていて、そのスクリーンは遠くからでないとカメラに収められないほど大きい。空の青さとスクリーンの白さが美しいコントラストを描く。敷地内の広い地面はうねうねと波打っていて、車を停めた時に車内からスクリーンを見やすいように設計がされていることもこの時に初めて知った。野球場のように広く、円形を描く敷地内の真ん中にぽつんと立ち、なにも写らないスクリーンを見回してはその度に感動をしてしまう。後ろを振り返っても、横を見ても真っ白いスクリーンが見える。映画館の清掃員らしき人がこちらに向かってにこやかに遠くから手を振ってきて、僕もそれに対して笑顔で手を振り返す。ここには青い空と白いスクリーンと風の音しか無いのだけれどこれ以上豊かに感じられる空間も無いだろうと思う。ここで上映されるであろう映画や、既に何十年にも渡り上映されてきた映画、それを見て育った子供や大人たち。この壁も天井もない大きな空間の中にしっかりと残っているその時間や空気は僕に大きな感動を与えてくれた。
自分がアメリカに来たいと思った大きな理由になっていた写真家達、例えばショアやエヴァンス、ロバート・フランクといったアメリカの権化のような人たちの写真を見るにつれて、必ずこの国の空気を吸わなくては行けないんだという思いが強くなっていった。そして僕が一番好きな写真家は、と聞かれた時に真っ先に名をあげるとしたらウィリアム・エグルストンと答えるだろう。エグルストンはその生涯において生まれ故郷であるメンフィスからほとんど出ていない。息子と2人で街を車でドライブしたり、歩き回りながら撮った写真が彼の写真の大半を占めている。彼の息子や奥さん、親族、知り合い。ライフイベントや日常の中で折に触れてカメラを構えそうした人たちを写す。何気ない街角やゴミ、車やダイナー、モーテルやサイン。アメリカ的と思われるモチーフもどこか違和感があるように思えるのは、アメリカに来て実際に彼の見てきた風景に近いものを自分で眼にした時だった。ユルゲン・テラーがエグルストンとの思い出を語るフッテージを見たことがある。エグルストンに憧れた彼が実際にメンフィスを訪れた時のことを語っていて、彼の言うことはただ一言「It is fucking boring!」だった。「彼があんなに素晴らしい光景を撮っていたんだから期待してメンフィスに言ったけれど、何もないクソほど面白くない場所だったよ」「ある日パーティで彼がただ一度だけシャッターを切った瞬間を見たことがある。ずっと椅子に座っていたのにおもむろに立ち上がって、そばにあったゴミ箱を写真に撮ったんだ。しばらくして彼が写真集を出したから中を覗いてみるとそのゴミ箱の写真があったんだよ!それがめっちゃ綺麗でさ、信じられるか!?」と興奮気味に語っていた。僕がメンフィスに来たのはエグルストンが生まれ、写真を撮りつづけてきた場所を見るためでもある。そしてこの街の住宅街を少しだけだけれど歩いて見て回って思ったのはテラーと同じことだった。何も特別な瞬間などなく、アメリカの紋切型のごく普通の住宅街だった。彼はアメリカ的なモチーフを撮っているのではなく、見えるものを感性に従って撮っているだけだったということをこの時に「理解した」。今まで写真集を見ていて感じていた彼の「アメリカ的な風景」はただの感傷的な風景でも、記録しておきたかった古き良きアメリカでもない別のものだとわかった。そして彼の表現したいものが全くを持って言葉が追いつかない領域にいることも同時に理解した。わかったというのは何かを読んで情報を頭にいれるということではなく、自分の内側から湧き上がる根拠もない確信のようなものだった。それは自分の中では何より正しいと思えるもので、おそらく今後もその意見が変わることは無いのだろうと思う。彼の撮ってきた車や古びたサインを目の当たりにした時、彼のようにはどうしたって切り取ることができない。彼が他の写真家と違うところは、写真を撮ろうだとか何かを表現しようということと全く逆のことが成立しているところで、それはつまり彼の撮ったものが写真や表現と呼ばれるようになることだった。彼の写真は何がどうしてその被写体をその画角で撮ったのかが理解することができないと思うことが多々ある。誰が三輪車を見かけた時に地面に這いつくばって仰角で撮ろうとするのだろうか。彼の眼がつま先や指先にでもついているのではないかと思うくらい、普通の人間の視点からかけ離れた精度と発想で写真が撮られている。煙に巻こうだとかそういう浅はかな発想でもなく純粋に彼自身の感性で切り取られた写真の美しさというのは見れば見るほどにわけが分からなく、そして恐ろしいとも思える対象になった。
もし、この街を歩いていて奇跡が起きて、エグルストンに会えないだろうかと思っていた。そう思ってこの街で最後に立ち寄ったのはウイリアム・エグルストン財団のあるアパートメントだった。何度もその赤いレンガでできたアパートの前をうろつきながら人が出入りするのを伺っていたが彼は現れなかった。意を決して電話をかけてみると「こんにちは!ウイリアムエグルストン財団です。」という声が聞こえてきたが、その後には「御用のある方は音声のあとにメッセージを残してください」と続いていた。彼の息子の声だった。残念だったけれど、ここでエグルストンに会えていたらもうアメリカに来る理由も失ってしまっていたかもしれないと思う。その思い出はあまりにもできすぎてしまっているだろうから。