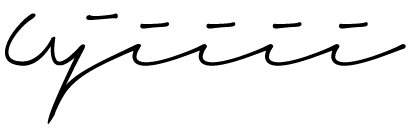SEE EVERYTHING ONCE / TRIP TO SOUTHERN DAY22
ミシシッピ川に沿って北上してミシシッピ州に入る。ミネソタ州から続くハイウェイ61ことブルースハイウェイを通って北上していく。この61号線沿いに著名なブルース・ミュージシャンやブルースの曲が生まれたらしいのだけれど、その理由の一端でもこの日のうちに知ることはできるだろうか。ふと気づいたが、この道はなにやら不穏な雰囲気に包まれている。端的にいえば陰鬱さが全体に漂っているのだけれど、これは曇りで空が灰色のせいではない気がする。行けども行けども何も見当たらず、あるのは綿花のプランテーションくらいなものだった。途中で通り過ぎる街も同様に陰鬱な雰囲気を醸し出しているだけでなく、おそらくは本当に治安が悪いのだろう。ガソリンスタンドに立ち寄って見かけたのがクレジットカード不正利用注意のサイン。スタンドに停まっている車はどれもボロボロの古い車ばかりだし、スタンド脇のキオスクも、僕に続いてスタンドに入ってくる車からも、白人は一人として見かけることはなかった。街の中には質屋と消費者金融、100円ショップが立ち並んでいるし、崩壊しかかった家の前では平日の昼間からおじさんたちが屯して煙草をふかしてうろついていたりする。前回の旅で立ち寄ったインディアンリザベーションを更に濃くしたような陰鬱さが街全体を覆っていた。
ミシシッピ州には2つの大きな川が流れてていて、その一つはミシシッピ川、そしてもう一つはヤズー川という。その2つの大きな川の間には綿花のプランテーションが広い面積に渡って作られている。収穫の終わった綿花は黄色いビニールに包まれて直径2m、長さ3mくらいの大きな円柱の形にまとめられ畑の上にゴロゴロとたくさん転がっている。アメリカ南部の主要産業が綿花だということは誰しもが習う。植民地として入植した白人が非常に安い賃金で現地人を利用し、その後急速に拡大した綿花栽培よって労働人員が不足すると黒人を奴隷として使役した。大赦法による南部のアフリカ系アメリカ人の選挙権の剥奪、過酷な労働環境、圧倒的な貧富の差に行き過ぎた差別意識。この地域を見ていると21世紀になった今でもその名残が強く残っていることが伝わってくる。ロバート・ジョンソンが魂を売ったと言われるクラークスデールの街、ブルースの聖地と呼ばれるここでさえも陰鬱な雰囲気に包まれていたように思う。この街の周囲の状況がなぜここまで荒廃しているように感じられるのかは明らかだったし、おそらくは南部のこのブルースハイウェイ沿いは似たような状況が続くのだろうと思った。ブルースは奴隷として生活していたアフリカ系アメリカ人の人達によって作り出された労働のための歌をベースにしていたと、以前見たテレビ番組でどこかの音大の教授が言っていたことを思い出した。それはゴスペルやソウルといった黒人音楽と呼ばれる音楽ジャンルについても同様だった。彼の授業の中である黒人歌手の曲を授業で聴き、その感想を一言で共有するというシーンがあった。生徒が口にしたのは「愛」「平和」「神」「力」と言ったキーワードだった。その教授は言った「文字の読み書きもできない黒人の作った音楽がこれだけ多くのインスピレーションを生み出すことができる。これが音楽の持つ力だ」と。自分の兄にも似たようなことを教えられた覚えがある。僕が音楽について自分で知識を得ようと思っていた頃、ブルースという音楽はアメリカの貧しい農家の人たちがなぐさみのために電気を使わない楽器を使って生み出したものだと。生涯で一人一曲、ないしは一枚のLP、そうしたものを生み出しながらブルースは草の根的に発展していったものだと。ブルースという音楽はブルーという色が示す通り、元々は哀愁や悲しみを表現するための音楽だった。徹底的に冷遇された環境下で作られた音楽だけれど、時代とともに悲哀ばかりではなく明るく前向きな曲も作られるようになり、一つの音楽のスタイルとしてアメリカという国に、そして世界に認知され、様々な音楽に影響を与えるまでになった。ヒップホップにしろ、R&Bにしろ、今アメリカで覇権を握っている音楽は黒人の人たちによって生み出されたものであり、それは抑圧や差别、冷遇された環境に対する抵抗として生み出されたものだ。そしてそうした音楽は教会や仕事場といったコミュニティで歌われながら根付き、何世代にも渡り大切に伝えられてきたものだった。僕がこのミシシッピデルタと呼ばれる地域で見たのはそうした音楽が生まれたルーツだったように思う。頭ではわかっているように思っていたけれど、本で歴史を頭にいれることと本物の雰囲気を見ることは大きく違う。本当の意味で自分のルーツでない音楽を理解することは難しいし、知っていることと理解していることの乖離は自分が思っていたよりも5億倍は深い。得意がっていたわけではないけれど、そうして生み出された音楽をある程度わかったつもりになって聴いていた自分が恥ずかしくなる。音楽は楽しむためのものだ、という姿勢は深い理解やその音楽の生まれた背景や本質的な部分への共感をおざなりにする。音楽の良し悪しをグルーヴやメロディ、その革新性やメッセージ性だけで評価するのではきっといつまでたっても進歩はないし、なおのこと自分の好みやノスタルジーだけで曲の善し悪しを決めてしまうことは姿勢としては正しいとは言えないだろう。より真摯にその音楽の成り立ちを理解し、共感しようと努力していこうと心に決めた。