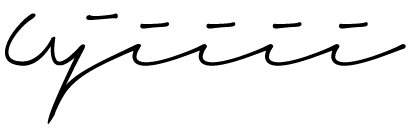SEE EVERYTHING ONCE -DAY21-
ハドソン川に添って北上しDia:beaconへと向かう。ニューヨーク滞在二日目にしてニューヨークから出るというなんとも言えないプランなのだけれど、このDia:beaconという美術館に来るのは長らく夢見ていたことだった。とある上野のカフェでこの美術館の図録を読んで、これまで見てきたどの美術館とも違う規模の現代美術専門の美術館だったことと、ナビスコの包装工場を改装して作られたということを知り、いつか必ず行かなくてはならない場所だなと思っていた。ハドソン川を北上するときには、この日のためにプレイリストに入れたダーティ・プロジェクターズのUp in Hudsonを聴きながらゆっくりとドライブをした。途中ご飯を食べるために、ビーコンの手前にあるコールドスプリングという小さな街のおしゃれなカフェでコーヒーと美味しいサンドイッチを食べる。街の外れにはハドソン川が流れていて、川沿いにはたくさんのボートやヨットが停泊していた。そよ風が吹いていて、ベンチに座ってゆっくりとタバコを吸ってから、念願のDia:beaconへと出発した。
結果から言えば、美術館を見切るのには4時間以上を費やした。ほぼ半日、広い美術館の中を歩き回り、解釈の難しい作品と対峙し続けたことにより脳が限界を超えて疲労し、喉は渇き、足は重くなった。SFMoMAを見たときもとても疲れたけれど、この美術館の圧倒的な圧力は今まで体験してきたどの美術館よりも大きなものだった。日本の美術館だと有名なアーティストを何人かピックアップし、それぞれの作品を1~2点集めてきてキュレーションをするけれど、この美術館で展開されているのは全く別のモノだった。各アーティストごとに部屋ないしフロアもしくは莫大なスペースが与えられていて、そのスペースに何点もの作品が展示してある。スケール感がまるで違う。これが私設の美術館であることがまず信じられない。ソル・ルウィット、ゲルハルト・リヒター、リチャード・セラ、ルイース・ブルジョア、ダン・フレイヴィン、河原温、ウォルター・デ・マリア、ブリンキー・パレルモ、ブルース・ナウマン、ドナルド・ジャッド。他にも超一流のアーティストの数え切れないほどの作品が設置してある。鑑賞する上で特殊なのは、これらの作品が自然光で見られるという点で、工場の大きな窓から差し込む光で作品が照らされる様子はとても詩的で美しいものだった。この美術館で一番印象に残っているものがあるとするならばそれは大きなガラス窓から入ってくる柔らかな光が美術館を優しく照らしている様子だったのかもしれない。地下のスペースすべてを使った蛍光灯の作品はもはやアートというより建築の一部のような気がしたし、外にでれば壁面にナウマンのアートが施されていたりもする。会場は広く、見ても見ても見きれない。迷路のように入り組んだ会場だから見逃しているものがないかどうかも心配になるから余計念入りに見て回ることになる。その結果、頭痛がするし、眼精疲労は酷いし、美術館を出た頃にはクタクタで、もう暫くアートもなにも見たくないような気持ちになった。ただ、この美しい美術館とたくさんのアートの組み合わせは世界を探してもここでしか見れないようなものだと思う。来る価値は十二分にあった。もしニューヨークに来たいという人がいるならば、是非この美術館に来るために一日かけてほしいと思う。
そのまま来た道を戻り、ニャックという街へと立ち寄る。この街はエドワード・ホッパーが過ごした街らしかった。街自体は何の変哲もない川沿いの街で、それなりに発達したスモールタウンという様子だった。彼の家は川の近くの通りに面した素朴な板張りの2階建ての家で、この日は改装中の工事のため出入りが出来ないようだった(ふざけんな!)。なんとなく彼の過ごした街は小さく廃れているようなイメージを勝手に持っていたのだけれど、実際のところそんな様子もなく、ほんの少しだけ寂しさの漂う川沿いの街だった。この街から彼はニューヨークへも行っただろうし、ケープコッドにも行っただろう。この街にもう少し長く滞在できれば彼の過ごしたこの街での生活の一部を垣間見えるような気もしていたけれど、あまり遅くなってしまうとニューヨークの渋滞で死ぬかもしれないと思い足早にこの街から出るしかなかった。この頃にはあたりは暗くなってきていたのだけれど、この街のすぐ近くにはパターソンという名前の街があった。その名の通り、この年に公開されたジム・ジャームッシュの映画の舞台となった街らしく、帰りがけに立ち寄ってみることにした。前情報によれば、この街は非常に犯罪が多く、その犯罪率の高さは全米トップ20に入るほどだそうだ。確かに、道は荒れているし、ガラの悪そうな人たちもチラホラと目につく。ニューアークやハートフォードにも似た雰囲気を感じるし、何よりもう夜が近くて車から降りてスラム付近をぶらつくのは危なすぎる。パターソンという映画タイトルの割には、ニューヨークで撮られた場所が多く、パターソンで撮影されたのはバスが故障するワンシーンのみだったのはこのときに気がついた。あの映画はアダム・ドライバーがバスドライバーで、彼がパターソンという街でパターソンという名前の役を演じる入れ子構造にこそ意味があるのであって、別にそれがパターソンじゃなかったとしてもなんの違和感も無いのだけれど、同時に必然性にも欠けるようにも思った。こうして僅かな時間でも、自分の知らない街の姿を見れるというのは自分にとっては大切なことで、その道中に窓から見えるモーテルやダイナー、薬屋やバーのネオンはいくら見ても飽きることはない。信号待ちをしている人々の装いや顔つき、人種。あらゆるものがアメリカの断片のように見えてくるのが幸せでならなかった。
夜ご飯は宿の側の廃れた中華料理屋で、油っぽくて味の薄い、だけど量だけは3人前くらいある、典型的なアメリカで食える中華料理を食べた。持ち帰り用の発泡スチロールの箱に汚く盛られたチャーハンと炒め物は、3口食べるとお腹がいっぱいになる。食べても食べても減らないし、どこまでも同じ味が単調に続く。それと同時にこの味気無さこそが味だろうという気持ちになるのは、アメリカ文化かぶれの自分がこの旅を楽しめている証拠だった。中華料理屋の前の大通りには小銭やビールをねだる浮浪者がうろついていて、ゴミはそこらじゅうに落ちていて車の通り過ぎる風に揺られて舞い上がり、フルーツ屋さんは深夜も近いというのに仰々しいネオンと蛍光灯を点けながら排気ガスで汚れた果物を売っている。帰り道に家の近所の駐車場に停まっている車を見てみると、リアガラスは無残にぶち破られていたりする。足早に宿に帰り、コンビニで買ったブルックリンラガーを飲みながらこうして日記を書いていると、ニューヨークの生活をほんの少しだけ味わえているような気がしてくるのだった。