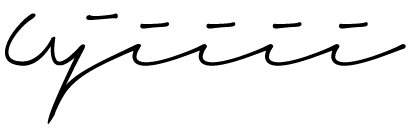TRIP TO TAIWAN -PENGHU~KAOSHIUNG / DAY12-
DAY12
朝食を食べに澎湖島の中心へと向かう。細い路地にいくつかの商店が軒を連ね、どの食堂からも美味しそうな匂いが漂ってくる。昨日行った映画館の近くの食堂にとりあえず入り、朝ごはん用の定食を頼むと、300円くらいしか払っていないのにスープやらパンやら揚げ物やらがまとめてとんでもない量が出てきたので思わず面食らってしまう。ポリシーとしてご飯は残さない主義なので、満腹感を感じる前にどんどんと詰め込めるだけ胃に詰め込む。台湾の人たちは毎回こんなにたくさんの朝ごはんを食べるのだろうか?台東のときも思ったけれど、どう考えてもカロリー過多だろう。重たいお腹を引きずりながら、スクーターに乗り、澎湖島の北の果てにある灯台を目指す。灯台を目指す理由は特にないのだけれど、スクーターで1時間も薦めば着いてしまうと言われたら、それはいかないという選択はできないだろう。
昨日と同様、各諸島をつなぐ橋を渡るたびに吹き飛ばされそうな強い風に煽られる。風を避けようとして俯くものだから、ろくに前も見えない中でぐんぐんと進んでいく。ぐんぐんと、といっても時速にしたら30キロくらいしかでていないのだけれど。道中で見える景色は昨日と変わらず美しい。広い空と青い海、たまに見える廃れた集落や、野放しにされた大きな家畜の牛や山羊。いくつか小学校を見かけたけれど、きっと全生徒を合わせても30人もいなさそうな気がする。北の果てにあった灯台は軍事施設として使われているようで、基本的には出入り自由なのだけれど、軍で使われている建物には金網が張られ番犬が猛烈な勢いで威嚇をしてきた。そういえば、花蓮でも台東でも何十分かに一回は頭上を戦闘機がけたたましい音をたてながら飛んで行くのを何度も見かけたし、軍の基地もいくつか通りがかった。アメリカで出来た台湾の友達はみんな徴兵を経験していたし、その経験を面白おかしく語ってくれるのが好きだった。この灯台は小さくて、5分もあれば見て回れるほどだった。おそらく朝礼用に使われていた小さな演説台が施設の真ん中にあり、無人の施設内でそこに立って下を見下ろすとなんだか気恥ずかしい気がしてくる。灯台は崖の上につくられているから、そこからの長めは素晴らしい。台湾の北東部の海が遠くまで見渡せる。小さな船が遠くに1隻、キラキラと太陽の光をうけて輝く水面の上をゆっくりと進んでいる。海鳥が崖につくった巣に目掛けて飛んで帰ってきたり、そこから飛び立ったりしている。もともとすごく強い風が吹いているのだけれど、その風が崖にぶつかることでより強い上昇気流となって崖下から拭き上げてくる。だから、海を見渡していると耳元で風が爆発するような音がずっと鳴っているように感じる。
灯台から戻る途中に崖下に小さな港町を見つけ、そこでコーヒーを買い(セブンイレブンがあった)、舟の手入れをする漁師の人たちに混じって少しだけ休憩をする。舟の形も装備も、日本の漁船とそっくりで、たくさんの電球をつけた舟はきっとイカ釣り漁船だし、どの舟も年季の入った大漁旗を強い風にはためかせていた。きっと波は日本よりもずっと高いだろうから、どれだけ熟練した漁師でも船酔いは避けられないだろう。港の前にあった小さな休憩スペースで休んでいたときに、そのベンチの下にエナジードリンクらしき瓶がものすごい量でポイ捨てされていたのだけれど、今思えばあの瓶は酔い止めだったのかもしれない。
今日はなんの予定もなかったので北端からホテルまで南に適当に下っていくことにした。大きなウミガメが地下の水槽にたくさんいるというちょっとよくわからない不思議な廟に行ってみたり、廃れた小さなリゾート街にいったり(真新しいホテルが建てられている途中だった、、、)、真っ白い砂浜の広がる小さな小さな浜辺に行ってみたりした。別の港の岸壁を散歩していると、漁師の人たちが両手両足を使って地引き網を編み直しているところだった。海鳥の声と、優しい日差しと、暖かい気候がその雰囲気ととてもマッチしていて、そこだけ時間がゆっくりと流れているような感覚を覚える。もはや観光客が来るエリアからはだいぶ外れているから、これがこの島の本来の姿なのかもしれないと思ったし、そうであってほしいと思う。ただ、風はもう少しだけ弱くても良さそうだ。
5時にはホテルに戻って高雄行きの飛行機に乗らなければならないから、早めにホテルに戻って帰り支度をする。ホテルの前にあったカフェでやたらと苦いコーヒーを飲みながら一息つくと、あたりは暗くなり、空は終わりかけの夕焼けの色をしていた。送迎バスのおじさんは相変わらずニコニコしていて、顔に似合わず中国語のヒップホップをかけながらご機嫌で空港まで送迎してくれた。飛行機に乗ると瞬間的に眠りに落ちてしまい、瞬き一つする間に高雄の空港に着いてしまった。
高雄の中央公園の脇には、「原宿」と「新堀江」というエリアがあり、もちろんそこは日本の地名から取られているのだけれど若者が集まる場所になっている。その裏の方にある台湾の伝統的家屋をリノベーションした素敵なホステルに泊まることにした。コンクリート造の無骨で堅牢な建物なんだけれど、鉄格子につけられた装飾のあしらいや、各所に施されたタイルの柄や色合いが素敵でまったく無機質な感じがしない。大きく開けたベランダは20㎡くらいはあるだろうか、ゆうに10人は入れそうなくらい広くて、そこで夜風を浴びて、街の喧騒を聞きながらタバコが吸えるというのだからこれ以上何も言うことはない。ベランダで一息ついていると、通りを挟んで向かい側に並んでいる古いアパート群の建物すべてが素晴らしかった。合理性を欠いた設計で、わけのわからない不安全なはしごが屋上に向かってつけられていたり、屋上にプレハブの小屋を乗せてみたりと、おそらく違法建築なのだけれども、そこに住む人の暮らしが想像できるところが愛らしい。合理性と費用対効果を追い求めた日本の建売住宅や、買う人のことが想像出来てない紋切型の新築アパートとは偉い違い。
一息付いた後に、せっかく高雄まで戻ってきたので15分ほど歩いて夜市へと向かうことにした。ふらりと立ち寄った屋台の水餃子を食べたのだけれども、これが革命的に美味しく、食べた瞬間に思わず笑ってしまった。飾り気のない店内というか屋外というか、路地に雑然と置かれた食卓にはたくさんの人が座って美味しそうに水餃子を食べている。メニュー表には水餃子と酸辣湯しかなく、これほどシンプルな屋台もみたことがない。一家で経営しているのか、10歳くらいの男の子がせっせと器を運んだり会計をしたりと大忙し。20個の餃子と酸辣湯はあまりに美味しくて一瞬で食べ終わってしまう。食れば食べるほど腹が減るこの魔法の餃子のことは一生忘れないだろう。迷った末、恥を捨ててさらに10子ほど注文したら、おじさんが嬉しそうにこちらを見ていた。目の前で十字を作ると餃子十個の意味になるらしいので、両手で十字を作っておじさんに合図をした。
ホステルの近くに24時間営業のカフェを見つけた、名前はグッドマン。このグッドマンすごいところは、24時間営業というだけでなく、道路に面したところにパティオがあり、さらにその内側にテラス席がある。そのいずれもが喫煙可能という駄目な人間仕様のカフェだった。飲み物も食べ物も、ないものが無いというくらいすべてが揃っている(鍋すら注文できる)。このパティオで夜の高雄の雰囲気を感じながら、少しだけ肌寒い風とスクーターのテールランプを見ながらコーヒーを飲んだ。これほど贅沢でゆるやかな日常というのはなかなか無いだろう。やはりこの高雄という街は最高だ。
-------------------
祖父の容態は日に日に目に見えて悪くなってきている。痛みが激しくなってきているようで、より強い鎮痛剤としてモルヒネが投与されるようになった。意識の混濁を自分で悟った祖父は、枕元にあった紙とペンを手に取り、住所を口に出しながら、震える手で何度も何度も住所を書こうとしていた。その文字は、かつて達筆だった祖父の文字からはかけ離れたものだった。丁目以降は思い出すことが出来ず、何度も「岩沼市二木」というところで止まってしまっていた。その震える筆跡と、何度も書きつけられた未完成の住所を見ているとやり場のない悲しみが溢れてくるが、それと同時に祖父の意志の強さを改めて感じることが出来た。自分にとって不思議だったことは、死の淵に片足をかけた祖父がまず記憶にとどめようとしたのが自分の家の住所だということだ。僕が暮らすこの家は、祖父にとっては実家ではない。祖父が退職後に余生を過ごすために、そして自分の娘のために立てた家だ。この田舎のニュータウンに建てられた、少し大きくて、広い庭のある、目立った特色もない家は祖父にとってはかけがえのない帰る場所なのだろうと思う。これは自分にとってはとても重要な示唆となる、僕はこれまで「きっとここが帰る場所」というのは必ずしも空間を指すものではなく、それは人物だったり時間軸だったり、その人自身で定義し見つけ出すものだと思っていた。しかし祖父にとっての実家は空間であると同時に人もそこで過ごした時間も内包しているということにほかならない。おそらくその人にとって理想的な空間とはかくあるべきであり、そうした空間を見つけることが、もしかすると人が幸せに生きるということと関係しているのかもしれない。
「迷惑ばかりかけている。人の優しさがありがたすぎて負担になる」
祖父はそう言って、僕と母を病室から追いやった。母が見せてくれた祖父が書いた住所の下には、ぐしゃぐしゃになって入り組んだ線の中から「知史」「浩史」と祖父と暮らした2人の孫の名前が、震える文字で書いてあった。