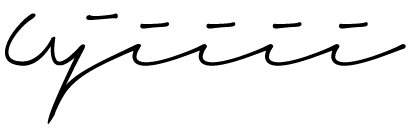ALASKA PART6 -CHATANIKA LODGE-
口とお腹の中がぎっとりとした油でみたされたところにコーラを勢い良く流し込む。口の中の油をさらっていき、胃の中で炭酸が弾ける。机の上に眼を落とすと、紅白のチェック柄のテーブルクロス、そして上にはケチャップとマスタードのボトルが並んでいる。それはまるでエグルストンの写真のような、いかにもといったアメリカのダイナーの雰囲気を醸し出していた。100席以上はあろうかという広い店内にお客はまばらに入っていて、空いたテーブルの下や椅子の隙間をオーナーのおばさん(ペギーさん)の飼い犬たちが自由に走り回っている。窓の外は雪景色で、強い日差しが雪に反射して、あちこちから眼に飛び込んでくる。しかし広すぎる店内に光は循環しきらず、光がこもったように優しく空間を照らしている。店内の壁にはアンティーク品やお土産、そしてこれまで訪れた人たちが残した$1紙幣が数え切れないくらい貼り付けてあった。更に季節外れのクリスマスの照明やオーナメントが3月だと言うのにキラキラと輝いていた。店の奥にはプール台とレトロなアーケード、ダイナーのエントランスの脇にはこじんまりとしたステージがあり、次の演奏を静かに待っているように見えた。
自分の部屋に戻る。木製の家具や壁、金色の心中で縁取られた鏡、ひっそりと佇むルームランプ。赤ワインのような色をしたカーペットと、その色に揃えられたブランケット。ブラインド越しに光が差しこみ、ベッドの上に縞模様の影を落とす。決して広くはないが、なんて落ち着く部屋なのだろうと思った。何もないけれど何の過不足もない、最高の空間だった。
ベッドの上に横になり本を開く。旅も半ばを迎え、自分がこれまで読んできた深夜特急ももう半分を過ぎている。この本の読み終わりが旅の終わり。この空間で本をただダラダラと読んでいるうちにあっという間に残り1200Pは終わってしまうだろう。沢木耕太郎は観光名所をえ巡るよりも、その土地の映画館や食堂、公園などにいって時間を潰すことを旅の目的にしていた。一見無為に見えるその旅は、今の自分のしていることと変わらず、背中を押されたような気がする。旅を始める前に一切の計画を諦めてしまった自分をただ肯定しているだけではあるのだけれど。
この旅に持ってきた本はもう一冊ある、それは長田弘著『アメリカ61の風景』だ。著者が20年以上かけてアメリカを車で旅した記憶がみずみずしい言葉と鮮やかな感性で描き出されている。1州を残し全ての州を回ったと本の中で紹介されているが、おそらくその1州とは厳密には言葉にされていないがアラスカ州だと思う。駒澤敏器著『語るにたるささやかな風景』も自分の好きなアメリカ旅行のエッセイなのだけれど、これはどちらかというとスモールタウンを巡ったときの人々との交流や訪れた空間の記憶を綴っているのに対して、『アメリカ61の風景』は広大なアメリカという土地の空虚さに対して、自分の記憶を紐付けながら美を見出していくエッセイになっている。例えばそれはどういうことかというと、何もない広大な道路や砂漠、山並みを見たときに、著者が本を読んで感じていたことや、その土地にまつわる逸話、本の中に描かれていた光景が立ち上がってくることだったりする。アメリカ中の広い景色、その差異を如実に描写できるのは土地に紐付いた記憶こそがなせることだと思う。そして長田さんの眼と文章を通して、僕はその土地に対して思いを馳せる。おそらく普通にみれば何も変わらないであろう、ただの道路や山がまばゆい輝きを伴いながら自分の中に姿をあらわす。
本を閉じて当たりを見回すと、そこかしこに懐かしさや暖かさが感じられる。この場所に来たことはないのになぜか身近に感じられたりするのは、僕の記憶が少なからずこの場所に近い空間や雰囲気を知っているのだろう。それは映画で見た光景だったり、本で読んだ一節だったり、古い雑誌の切れ端に載っているようなさもない写真だったりするのだろう。
ふと気づくと、部屋の外から物凄い勢いでひどく汚い言葉が聞こえてくる。2秒に一度くらいのペースで「F**K!! Son of a bit**」のようなスラングが大声で叫ばれている。いかにもアラスカの荒くれ者といったような声色と語気の強さに思わず笑ってしまう。この声ですら何かの映画で見たような気がするからだ。