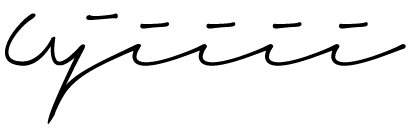SEE EVERYTHING ONCE / TRIP TO SOUTHERN DAY17
久々にモーテルに泊まったものだから無駄にシャワーを浴びすぎたり、テレビを見てしまっていて夜更かしをしてしまった。そのせいで朝早くに起きてオースティンの街をゆっくり歩こうと思ったのに気づけばチェックアウトギリギリの時間になってしまった。スーパー8というチェーンのモーテルは同じくチェーンのモーテル6と違い料金に朝ごはんが含まれている(のでどちらかを選ぶとしたらスーパー8がオススメ)。どのスーパー8でも同じ朝ごはんが提供されていて、シリアルやワッフルなどアメリカらしいメニューが並んでいる。コーヒーや牛乳もついているので、寝覚めの良い一日をスタートさせることができる、はずだったのだけれど朝ごはんは基本的には朝9時までに食べ終わらなければいけないため、この日は何も食べられずにモーテルを出立することになった。
郊外のモーテルからオースティンのダウンタウンまで車で15分ほど走っていく途中、ハイウェイの近くで路上に躍り出てきた黒人のお兄さんに話しかけられる。話を聞くと信号待ちの間に窓を拭いてやるから金をくれよ、ということだったのだけれどガスを入れた時に自分で窓を拭いたばかりだから丁重にお断りをしておいた。ダウンタウンに近づくにつれ、道路脇に同じような人たちをたくさん見るようになる。高架下には寝袋を敷いて寝ている人がいるし、スーパーの近くでメッセージボードを携えながら施しを待っている人たちもたくさんいた。オースティンのダウンタウンの駐車場に車を停めて街へと繰り出すと、予想に反して道路はガラガラだった。有名な街だからもっとたくさんの人たちで朝から賑わっているものかと思ったけれど、案外そうでもないらしい。タトゥーショップやカフェ、フードカート、レコード屋がポツポツと見えると非常にポートランドとの似ている街だなという印象を受ける。旅の前にテキサス出身の友達にオースティンについて聞いてみたところ、「オースティンはテキサスの中で唯一の、そして一番変わった場所だよ」と言っていたのを思い出した。基本的にテキサスの人たちは保守的かつ敬虔な人たちが多いのだけれど、オースティンだけはそうではないらしい。人種の比率や年齢分布を見ても、そして街の中を歩く人達の姿を見てもそれはひと目でわかった。テキサスといえばバーベキューなのだけれど、例に漏れずこの街にはたくさんのバーベキュー屋があった。そして変わっていることといえば、どのバーベキュー屋でもライブスケジュールが外に貼り出されていることだった。小さなバーやパブにも同様にライブスケジュールは貼り出されていた。その理由はオースティンはSXSWでも有名な音楽の街だからだ、そしてこの日僕が着ていたのはおろしたてのダニエル・ジョンストンのTシャツだった。オースティン大学の近くには「Hi, How are you?」というおなじみのダニエル・ジョンストンが描いた大きな壁画がある。僕がダウンタウンを歩いている間にも小さなダニエル・ジョンストンのイラストが道路や壁の小さな隙間に描いているのを何度か見かけた。彼が活動し、そして逮捕、収容されたのがこの街であることから、ダニエル・ジョンストンはオースティンを代表するアーティストだという人もいるくらいだった。だから、非常に浅はかで馬鹿馬鹿しいのだけれどこの日このTシャツを着て街を歩くことを実は少し楽しみにしていた。街をくまなく歩いてレコード屋があれば入り、スリフトショップやビデオ屋があれば入った。レコード屋では若い女の子が見覚えのあるレコードを手にはしゃいでいて、それはペイブメントのスランテッド・エンチャンテッドだった。その絵面は控えめに言っても最高だった。そして結果から言えばその日、来ているTシャツに突っ込んでくる人は誰もいなかった。それはないでしょう!
お腹が減ったので、いい感じに廃れたメキシカンダイナーを見つけたので奥の目立たない席について注文をする。ぶっきら棒な接客の中にもどこか優しさがあり、店員とのやりとりにはユーモアが溢れていた。最初はガランとしていた店内にもお昼が近づくと次々に常連らしき人たちが入ってきて、テイクアウトをしたり、席に座って店員の人たちと世間話を始めた。そうした日常の当たり前の光景、そして人々の時間の過ごし方が非常に素晴らしかった。僕の向かい側の席では何かのセールスの話を始めてしまう人もいれば、同僚とのランチついでに仕事の話をしている人もいた。もちろん近所の友達同士でわいわいとやっている人もいれば、そんなに急がなくてもいいのにというくらい急いでブリトーを食べて出ていってしまう人もいた。そういうのを群像とでもいうのだろうか、一つ一つの景色があまりにも自然で、それが自分にとっては逆に新鮮に思えた。僕が頼んだフジタスは少しだけスペシャルなトッピングをお願いしたので、美味しそうなお肉を始めとしたたくさんの具材がぎっしりと詰まっていた。お腹が減っていたのであっという間に食べ終わってしまい若干手持ち無沙汰になってしまったので、付け合せで出てきたチップスにサルサソースを付けてバスケットに盛られた分を全部食べきってしまった。店員の黒人のお姉さんに「おかわりいる?」と笑いながら言われたけれどお断りをして会計に進んだ。会計用のレジの脇にはガラスケースがあり、その中にはお店のノベルティであるTシャツや帽子が売っていた。どうしてもこの店のことを忘れたくなかったので、なけなしの金をはたいて帽子を買ってしまった。いい店のノベルティはかくあるべき、というどこかオフビート感の漂うおじさんのイラストの刺繍の入った帽子は今後ずっと被っていたいと思うだろう。
街の真ん中を流れるコロラド川を見にいくと、やはりこの街はポートランドに似ていると改めて思う。川が流れている街に悪い街はない、それはこの川沿いの風景を見下ろせばわかる。そこで犬の散歩をしたり、おしゃべりしたりしている人たちを眺めながらゆったりした時間を過ごしたあと、車に戻る前にカフェに入って一休みをする。オースティンのカフェはどこもだいたいヒップな雰囲気が漂っているのだけれど、僕が入ったカフェも例に漏れずとてもヒップだった。カフェは混んでいたので別のところにしようかと思ったのだけれど、店員の若いお姉さんがあまりにもおしゃれで綺麗で可愛かったし、何よりすごくフレンドリーで列に並ぼうとした瞬間からずっと話しかけてきてくれたので出て行く理由がなくなってしまった。もはや定形と化した旅の話をつらつらとしつつ、出てきたカフェラテを一口味わうと、とても美味しくてびっくりした。カフェの全体が見渡せる位置に席を取り、けちくさくゆっくりとカフェラテを味わう。お姉さんが可愛いことを差し置いたとしても、このカフェラテは地上最高の味だったと思う。一息ついたところで、浅倉から渡されていたユリイカに掲載されたミヤギフトシさんの書いたエッセイを読み始めた。ミヤギフトシさんのことを知ったのは大学の時に何かの拍子に偶然見た「American Boyfirend」と題されたブログと言うか、彼の作品だった。読めば読むほどに彼の描く文章に引き込まれていったことを覚えている。文章の間に挟まれる一切気取らない自然な写真と、歴史に紐付いた考察、そしてその時読んでいるものの雑記や、それに紐づく彼自身の記憶、文中に引用される美しい言葉やフレーズの数々。日常の延長から鳴る文章の題材の選びかた、言葉の選び方、そして引用や写真の選び方が非常に丁寧に行われている。彼のしていることは誰にもできないような突飛なことでもなければ、圧倒的な才能で誰かをねじ伏せたり感服せしめるようなものではない。ひたすらに丁寧に感じたことや調べたことを彼自身の感性でもって紡いでいる以上のものではない、はずなのだけれど、読めば読むほどにその一見普遍的に思える文章や写真の中に、非常に掴みづらくも、儚く美しい彼自身にしか出せない色が見えてくることにすぐに気がついた。大阪にティルマンスの個展を見に行った時に、隣の会場で偶然に彼の映像作品を見たときはその叙情さに深々と感動したこともまた強く覚えているし、その時の感覚については生涯忘れ得ないだろうとその時に思った。彼のぎこちない日本訛の英語のナレーションと、過度に編集も色構成も変えられていないと思われる自然体な映像。その中でふいに流れるバッハやベートーヴェンの弦楽合奏曲が彼の個人的な思い出とリンクし、どうしようもないくらいに美しいと思った。彼の作品にはよく「アメリカ」という言葉が使われる、それは米軍基地のあった沖縄に生まれ育ったことが大きく関係している。そして彼の捉えるアメリカというものは、どうやら僕が思うアメリカとはどうやら違うらしい。僕が捉えるアメリカというのは僕自身が都合よく解釈したアメリカであって、それは本当の姿ではない。僕の思い描くアメリカと、彼の描くアメリカを重ねてみればその違いがよく分かる。僕の思い描くアメリカが穴だらけで歪な形をしたペラペラの円形だとすれば、ミヤギさんの思い描くアメリカは形の整った質量を持った円球のようなものだと思う。歴史も文化も、過去日本とアメリカとの間に生じた軋轢も含め、主観的な目線と客観的事実にを混ぜながら美しく誠実に描写がなされている。彼の作品に惹かれる部分があるとすればその叙情さやナイーブさよりも、彼の作品を通して見るとわかる学びや表現に対する誠実な姿勢であり、それが彼自身とアメリカとを繋ぐ糸ととなる。そしてそれはオースティンのヒップなカフェの片隅で読んでいる彼の一番新しいエッセイにおいても間違いなくそうであると言えるし、彼の過去の作品同様とても誠実で素晴らしいものだった。
数日前にとんでもない道を通ったせいで車の外も中も砂だらけになってしまったので、オースティンを出る前に洗車に行くことにした。オイル交換の表示も出ていたのでついでにオイルも交換してもらうことにしたのだけれど、どうやら旅を初めて17日目にして9000マイルくらいは既に走っているらしかった(オイルは通常3000マイルで交換が必要とされている)。今後トラブルが起きては困るということで、少しだけ良いオイルを入れてみることにした。ルビーチューブというカーメンテナンスの全国チェーン店に車を運んでいき、受付で手続きを済ませるのだけれど、この店に勤務している人全員の英語を全く聞き取ることができなかった。この時初めてテキサスに来てからまともに人と会話をしたことに気付いたのだけれど、テキサス訛というのがここまで強烈なものだとは思わなかった。会話を理解できるかどうかはおいておいて、とりあえず自分が言いたいことだけをひたすらに言い続ければだいたいの局面は乗り切れることはわかっているので今回も強硬策に出るほかなかった。オイルを交換した車はエンジンの加速が心なしかスムーズな気がする。少なくともあと1万マイルくらいは走らなければ行けない算段なので、途中で車が壊れたとかそういうことが起きてはシャレにはならない。
オースティンを出てまたお決まりの如くIN−N-OUTに立ち寄りバーガーとシェイクを頼み、休憩しながら『パリ・テキサス』の映像を見ていた時に改めてふと思った。特別なのは地名や住所ではなく、そこにある空間と時間であるということ。何か特定の空間を誰かにとって特別たらしめる要因があるとすればそれは思い出なのかもしれない。
少なくともこの映画に出てくる場所の全ては自分にとってはとても特別な場所なはずだった。自分が『パリ・テキサス』の足跡を追うことで感じていた何か空を掴むような感覚もおそらくそれに依拠しているのだろう。空をつかむような感覚とは、平たく言えば何かが欠落しているような感覚で、それは実際に自分が見た風景と映画内に現れた風景の差異のことなのかもしれない。物理的に近い場所にいけば何か感じるものもあろうと思えたけれど、その空間(かつて映画で見た)が既に失われていると非常に難しかった。ヴェンダースが過去に旅した道程の中から自分で空間を選び、映画内にその空間を使用することは彼自身のごく個人的な経験によって行われているものだと思う。その時点ではそれらの空間は少なくとも彼にとって特別なものであっただろう。逆に言えばそこが選ばれたということは何かしら選ばれる理由があったということで、それがその場所が特別だったも考えられるのかもしれない。彼自身によって選ばれた空間を映画の鑑賞者がみることで、その鑑賞者にとっても同様にその空間が特別なものになりえる。たどり着くことのできなかった「テキサス州、パリ市」はまだ見ぬ桃源郷として、映画の中に出てきた数々のアメリカ的なモチーフは、それそのものがアメリカ的らしさをこれ以上なく現す記号として、荒涼としたランドスケープは感傷を呼び起こすきっかけとして。更に言えば、その映画を見た鑑賞者がその時に感じたこと、たとえば誰と一緒に見ただとか、最初に感動した映画だとか、理解もできなかったのに背伸びをして見てみただとか、そういうごく個人的な体験が更にその映画自体とその中に映し出される瞬間をより特別なものにする。ふと思い出したり、映画をまた見直したりすることでその結びつきは更に複雑に、強くなっていく。それらの特別な属人的な体験と空間は記憶と感情によって結びついているのだけれど、実のところ決して綻び得ないものではない。脳内のシナプスのように複雑に絡み合っているそれらの要素(空間/時間/個人的な思い出)は、どれか一つの要素でも欠けてしまえば記憶や感情の流れは断たれて崩れ落ちてしまう。空間が失われるということはそのシナプスの結合をロボトミー手術のように破壊してしまうことなのだろう。その空間に内包されていた時間ごと消し去ってしまうというのは、実に悲しく、そして取り返しがつかないことだと気がついた。それはその場所に結び付けられた特別性をそのまま失うことであり、僕の体験した「欠落しているような感覚」の正体では無いかと思う。平たく言えば、僕が『パリ・テキサス』を見て特別だと思っていた空間がまるごと失われていたことによる喪失感の深さの問題だった。世の中にエル・ランチョ・モーテルは数あれど、おそらく『パリ・テキサス』を見ている人であればフォートストックトンの、あの美しいサインのある空間が特別であるはず。そしてそれは『パリ・テキサス』を見たという経験を通して、その特定の空間に個人の記憶が紐付いていることは必然のように思えた。その空間内で独自に経過した時間の流れ、つまり自分以外の誰かも含めてその空間内で過ごした時間の流れがおそらく雰囲気と呼ばれるもののある一面とも言えるのかもしれない。それはその空間内に付けられた何らかの痕跡、例えば煙草の染みや壁の傷や、そこに訪れる人達の会話だったりする。そして個人的に体験した時間、その空間と自分自身の記憶とが結びついたときに起きる感情が愛着なのかもしれない。その2点は特別さを感じる上において欠かすことのできない要素であることは間違いがないように思えた。こうした特別な空間は時間とともに作られる、しかしそれと同時に時間とともに失われてしまうことがある。それは人為的でもあるだろうし、天災のような破壊的な制御の及ばない何かの場合もあるだろう。だから自分自身が何か特別な空間を見出すことこと、言い換えれば新たな視点を獲得し、なんらかの詩学によって空間を特別にしていかなければいけない。裏を返せば特別な場所というのはどこにもなく、どこにでもその特別さというのは見出すことができると解釈もできるかもしれない。そうした空間を自ら生み出す、あるいは特別な空間を残すための努力は今後必ず必要になるだろう。名前のない風景や見慣れた光景をかけがえのないものに変えたニューカラーの写真家のように、自分自身の記憶と空間とを美しく紡ぐ長田さん綴る文章のように、そして個人的な感情を誠実に丁寧に時間の流れと結びつけるミヤギフトシさんの作品のように。